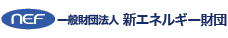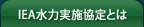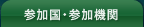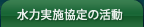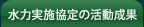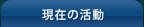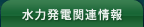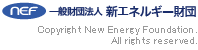水力実施協定の現在の活動
第6期 (2020~2024年)の活動
Task-9:水力発電の多様な価値
(オーストラリア、ブラジル、EU、フィンランド、日本、ノルウェー、アメリカ)
本Taskは、第4期から継続しているものであり、TM(活動リーダー)は、現在ノルウェーが暫定的に務めている。本TaskフェーズⅠでは他の再生可能エネルギー発電に対し調整機能を有し、また貯水池による流水管理や水域環境保全、地域開発等が可能な水力発電の価値を公正に認識・評価することを目標とし、活動を実施している。2018年から上記目標を深掘りする形で新たにフェーズⅡの活動が始まっており、以下のテーマについて検討を実施している。また、以下のテーマの中で、長時間エネルギー貯蔵(LDES)と水力発電の役割の検討や洪水調節・干ばつ管理の検討を実施している。
| Sub-Task-1: | エネルギー、グリッドサービスおよび適応 将来、低炭素社会に移行するエネルギー市場および電気系統における水力発電の役割と価値を評価する。 |
| Sub-Task-2: | 気候変動適応サービス 気候変動に関連するリスクを最小化または緩和するために水力発電の役割と価値を評価する。 |
| Sub-Task-3: | 定水力発電のバランスと柔軟性に関するロードマップの作成 Sub-Task-1とSub-Task-2の結果を文書化し普及させる。 |
| ・洪水調整と干ばつ調整を行う水力発電(Task-12と合同) |
| ・柔軟性と貯蔵 |
| ・水力発電のハイブリッド |
Task-12:水力発電と環境
(オーストラリア、ブラジル、中国、日本、フィンランド、フランス、ノルウェー、アメリカ)
本Taskは、第3期から継続しているものであり、第6期においても「貯水池における炭素収支の管理」(Sub-Task-1)のテーマで活動が続けられている。TM(活動リーダー)は、引き続きブラジルが務めている。2023年1月にTask-9との共同Taskの報告書「Hydropower providing flood control and drought management services under changing climate scenarios: Case studies」がIEA水力実施協定のウェブサイトにアップロードされたが、以降の活動を停止している。
≪成果報告書≫
| IEA技術報告書「Hydropower providing flood control and drought management services under changing climate scenarios: Case studies」(2023年1月、英文) |
Task-13:水力発電と魚
(オーストラリア、ブラジル、フィンランド、フランス、ラオス、ノルウェー、アメリカ)
本Taskは、第4期(2014年)から継続しているもので、オーストラリア(Hydro Tasmania社)、フィンランド(Kemijoki Oy社)、ノルウェー(水資源・エネルギー庁)、フランス(EDF社)が参加し、ノルウェーがTM(活動リーダー)を務めた。本Taskでは魚と水力発電は密接な関係があるが、最近の研究は魚種が限られていることや水力開発が今後も世界中で進められることからIEA水力を通じた国際協力プログラムとして活動を行った。2023年5月にIEA水力実施協定のウェブサイトにアップロードされた報告書「A Roadmap for Best Practice Management」をもって活動を終了した。なお、フォローアップとして、2023年にTask-19「水力発電と魚 2.0」が活動を始めた。
≪成果報告書≫
Task-16:Hidden & Untapped Hydropower Opportunities(オーストラリア、EU、日本、ノルウェー、アメリカ、スイス)
本Taskは、Annex-2を発展的に継続させたものであり2019年から新たに開始された。世界規模で隠れた水力ポテンシャルの開発を可能にし、それを支援するための枠組みを提供することを目的としており、活動は以下のとおりである。
| Sub-Task-1: | 包蔵水力量データの更新 新技術、追加データ、最新の経済基準、規制および環境の制約に関する情報ならびに改善された開発方法に基づいて、既存の包蔵水力量調査を見直し・更新し、追加データを特定するためのプロセスを検討する。 |
| Sub-Task-2: | 既存の水力発電所の性能向上 既存の水力発電所において、損失の低減および性能改善によって生じる出力増加の可能性を評価する。 |
| Sub-Task-3: | 非発電用ダムと水管理施設への発電設備の追加 水供給、灌漑、洪水調整用等のダムや送水管路、灌漑用水路等の水管理施設の未利用落差・流量を使用して水力発電設備を追加できるかを検討・評価する。 |
| Sub-Task-4: | Hidden Storage 既存の貯水池等を活用した中小規模の揚水発電設備を分散型電力貯蔵設備として追加できるか特定・評価する。 |
| Sub-Task-5: | 「Hidden Hydro」利用に関する水力発電技術の研究と革新 Sub-Task-1~3で適用された革新的な研究開発内容をまとめて評価し、将来の研究方向性と革新的研究の課題を策定する。 |
| 白書「Overview and major needs for identifying and acting on Hidden and Untapped Hydropower Opportunities at Existing Infrastructure」(2023年7月、英文) | |
|
| 白書 改訂版「Overview and major needs for identifying and acting on Hidden and Untapped Hydropower Opportunities at Existing Infrastructure」(2024年8月、英文、和文) | |
|
| IEA技術報告書「既存水力発電所の性能向上」(2024年9月、英文) | |
Task-17:Measures to enhance the Climate Resilience of Hydropower(日本)
本Taskは、2020年度で取組みが終了したAnnex-15「水力発電設備の保守および増強に関する意思決定」に引き続き、日本がTMとなって新たにTaskを設置すべく、令和2年度から活動を開始した。将来的に洪水規模の拡大が懸念される中で、発電事業者が取るべき、具体的対応策を調査する。調査結果は各国事業者にフィードバックされ、気候変動が拡大する中でリスク軽減に貢献することを目的としており、活動は以下のとおりである。
| Sub-Task-1: | 気候変動による自然災害リスク予測と、発電施設安全確保のための予防保全策と設計基準に係る評価(Sub-Task Leader:スイス) 洪水リスクを含む気候変動による災害リスクを予測し、これらに対する発電施設の安全確保を図るための予防保全策を調査する。調査では気候変動に伴うリスクとして、洪水量増大に加えて、大規模地滑り・氷河湖洪水による土石流等の自然災害リスク予測に加えて、発電施設、特にダム・洪水吐等の重要構造物の設計基準および予防保全策に対する評価を調査対象とする。 |
| Sub-Task-2: | 水力発電所の洪水被害軽減策(Sub-Task Leader:日本) 既存の洪水被害復旧事例から、災害要因分析に基づく復旧計画、経済性および施工技術面を考慮した改修方法に係る設計・施工上の課題を取りまとめる。また、予防保全としての発電施設の更新と併せて維持管理面における業務省略化や運用面における効率化等を付加した事例についても取りまとめる。 |
| Sub-Task-3: | 貯水池堆砂管理(Sub-Task Leader:日本) 排砂効率の向上に加えてダム下流の環境影響配慮に係る課題があり、特に同一水系発電所群における連携排砂については有効と期待されており、各発電所の運用に対する統合管理・モニタリングに基づく複合的な取り組みを調査し、課題と解決策を調査する。 |
Task-18:流域水資源の包括的利用のための意思決定支援(中国)
本Taskは、Annex-14を発展的に継続させたものであり2020年から新たに開始された。本Taskの主な目的は、水資源を包括的に利用するための意思決定支援システムの開発動向と関連する特性を分析し、交換プラットフォームを構築することで、将来の水資源意思決定システムの開発と適用に関連する事例を提供することであり、活動は以下のとおりである。
| Sub-Task-1: | 水文予測と配分技術 |
| Sub-Task-2: | 水力発電所の保守運用 |
| Sub-Task-3: | 流域の生態と環境保護 |
| Sub-Task-4: | 水資源の包括的な利用のための意思決定支援システム |
Task-19:水力発電と魚 2.0(アメリカ)
本Taskは、2023年5月に活動が終了したTask-13の後継として、2023年5月に執行委員会で提案された。執行責任者はノルウェーが務め、水力発電による魚類への影響の緩和策を調査することを目的とし、以下の事項について調査を進めている。
| ・地方、地域のスケールにおける環境フロー |
| ・魚類とその生息地のモニタリングのための高度な技術の適用 |
| ・水力発電の運転と魚類のリスク評価 |
| ・主要な利害関係者・組織との連携 |
| ・国際会議の場でセミナー/特別セッションを開催 |
| ・概況報告書の作成 |
| ・環境フロー、監視技術およびリスクt評価に関する調査報告書の発行 |
| ・最終報告の作成 |